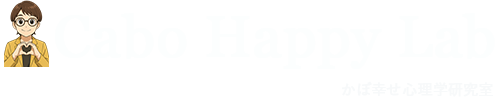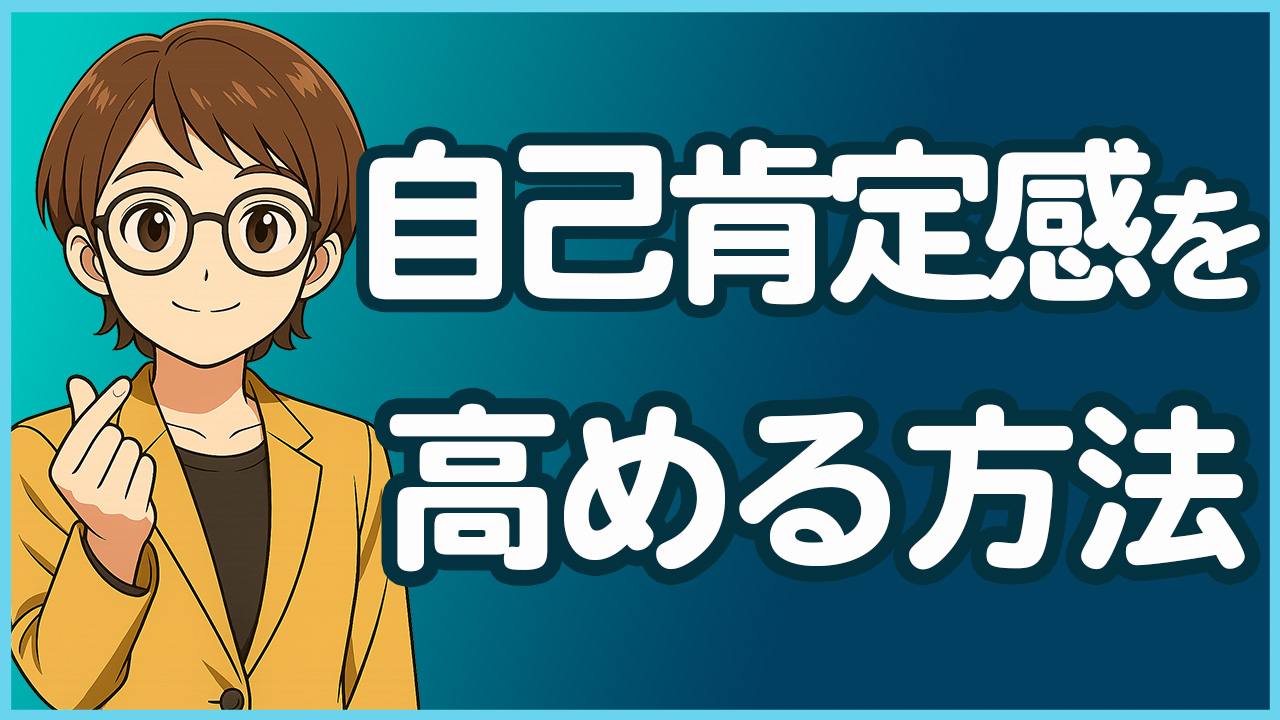部屋でひとりになったとき、ふとこんな気持ちが押し寄せてくることはありませんか?
「なんで私はこんなにダメなんだろう…」
「できないことばかりで、情けなくなる」
誰かに認めてもらいたい。
でも、自分では自分を好きになれない。
そんなふうに、心の中の“責める声”に疲れてしまっている人は、決して少なくありません。
はじめまして、公認心理師のかぼです。
私自身、10代のころ不登校を経験し、「自分には価値がない」と感じていた時期がありました。
その後、少しずつ心を回復させていく中で、教員として子どもたちに向き合い、今は心理師として「心が少しでもラクになるヒント」をお届けしています。
この記事では、「自己肯定感が低い」と感じているあなたへ、
心理学の視点と実体験をもとに、少しでもラクになるためのヒントをまとめました。
自己肯定感とは?「ポジティブでいること」ではありません
「自己肯定感」とは、自分という存在に価値があると感じられる心の状態です。
これは「自分が完璧である」と思い込むことではありません。
むしろ、できない部分や弱さも含めて、
「まあ、それも私だよね」と受け入れられること。
たとえばミスをしたときに「自分はダメだ」と決めつけるのではなく、
「誰にでも間違いはある」と考え直せる柔軟さ。
あるいは落ち込んだときに、無理に元気になろうとするのではなく、
「こういう気持ちになることもあるよね」と、ありのままの自分に寄り添える感覚。
自己肯定感は「3つの柱」からできています
- 自己評価:自分の行動や能力を冷静に見つめる視点
- 自己受容:うまくいかない部分も含めて自分を認める姿勢
- 自己信頼:困難にあっても「きっと大丈夫」と思える安心感
よくある誤解に、
「自己肯定感が高い=いつもポジティブ」というものがあります。
でも実際には、ネガティブな感情が湧いたときに、
それを否定せず受け止められることこそが、自己肯定感の本質です。
自己肯定感が低い人の特徴7選|あなたが悪いわけじゃない
では、自己肯定感が低い人にはどんな傾向があるのでしょうか?
よく見られる特徴を、7つにまとめました。
- 失敗するとすぐに自分を責めてしまう
- 他人の期待に過剰に応えようとする
- 褒められても素直に受け取れない
- 過去のミスを何度も思い出してしまう
- 頑張りすぎて燃え尽きやすい
- NOと言えず我慢してしまう
- 他人の評価に一喜一憂してしまう
これらは一見「真面目で優しい人」の特徴にも見えるかもしれません。
しかしその裏側では、自分を責めるクセや自己価値の不安定さが隠れていることが多いのです。
そして大切なことをお伝えします。
これらの特徴は、あなたが弱いからではありません。
私自身、不登校だった頃、この7つすべてに当てはまっていました。
両親の圧が強くて、自分の本音をずっと抑え込んでいたし、
ちょっとした注意で1日中落ち込んで、部屋の中に逃げ込んでいたんです。
つまり、自己肯定感が低いのは「性格のせい」ではなく、
そこには背景があります。
なぜ自己肯定感は低くなるのか?原因は3つ
自己肯定感が下がってしまう原因には、主に3つの要素が関わっています。
1)幼少期の家庭環境
完璧を求められたり、失敗を厳しく責められる経験が続くと、
「ありのままの自分では受け入れてもらえない」と感じてしまいます。
たとえば、こんな環境です。
- 100点を取って当たり前
- 兄弟や周りの子と常に比べられる
- 感情を出すと「わがまま」と否定される
こうした体験が積み重なると、
「本当の自分はダメなんだ」と心が思い込んでしまいます。
2)学校や社会の「評価文化」
テストの点数、成績、通知表などで評価され続けると、
「できること=価値」と刷り込まれてしまうことがあります。
本当は絵が得意だったり、人を笑顔にするのが得意だったりしても、
「それでは評価されない」と感じてしまう。
そして、できない部分ばかりに目が向きやすくなっていきます。
3)スキーマ(思い込み)の影響
自己肯定感を下げてしまう“心のクセ”として、次のような思い込みがあります。
- 「私は愛されない」
- 「頑張らないと存在価値がない」
- 「人に迷惑をかけたら嫌われる」
これらは無意識に心へ根付いてしまいます。
本来は自分を守るための考え方だったのに、
大人になってからは、かえって自分を苦しめてしまうのです。
自己肯定感を育てる5つのステップ|今日からできる方法
「じゃあ、どうすれば自己肯定感は高められるの?」
ここからは、実践しやすい5つの方法をご紹介します。
ステップ1:セルフトークに気づく
私たちの心の中では、1日数万回もの“独り言”が流れていると言われています。
「今日もだるいな」「どうせうまくいかない」など、無意識の言葉が積み重なると、心は確実に疲れていきます。
まずは、そのセルフトークに気づいてみてください。
紙に書き出すだけでも、感情との距離が取れるようになります。
「気づき」は、変化の第一歩です。
ステップ2:「できたこと」を記録する
自己肯定感が低い人ほど、「できなかったこと」に注目しがちです。
だからこそ、意識して「できたこと」を拾っていきます。
たとえば、こんな小さなことで十分です。
- 朝ごはんを食べた
- 顔を洗えた
- 外に出られた
- 今日はちゃんと休めた
「こんなこと当たり前」と思うようなことこそ、
あなたを支えている立派な一歩です。
ステップ3:自分に優しい言葉をかける
あなたの親友が落ち込んでいたら、何て声をかけますか?
その言葉を、そのまま自分にも向けてあげてください。
- 「そんな日もあるよ」
- 「今日もちゃんと生きてたよ」
- 「よく頑張ってるね」
人に優しくできる人ほど、自分にだけ厳しくなります。
だからこそ、ここは意識して“自分を味方にする言葉”を選んでみてください。
ステップ4:SNSを少し休んでみる
SNSは、基本的に「その人の良い瞬間」が切り取られています。
そこで比べて落ち込むのは自然なことです。
もしSNSを見るたびに苦しくなるなら、
思い切ってスマホを手放す時間を作るのも一つの方法です。
比べる世界から離れると、少しずつ自分の呼吸が戻ってきます。
ステップ5:自分の価値観で目標を立てる
「褒められるため」「認められるため」の目標は、苦しくなりやすいものです。
それよりも、あなた自身が「こうしたい」と思える目標を持ちましょう。
結果が出なくても、「取り組んだこと」自体に価値があります。
自己肯定感は、“評価されることで増える”のではなく、
自分の価値観を大切にしたときに育っていきます。
自己肯定感が育つと、心にどんな変化が起こる?
自己肯定感が少しずつ育つと、まず起きる変化があります。
それは「自分の感情をそのまま受け止められるようになる」ことです。
自分を責める時間が減ると、心の中が少しずつ穏やかになります。
無理して頑張るのではなく、「自分のペース」で取り組めるようになるので、結果的にパフォーマンスも安定していきます。
そして、他人と比べる必要が減っていくので、
SNSや人間関係で消耗する時間も少しずつ減っていきます。
自己肯定感は、ただ“気分が良くなる”だけではありません。
自分の人生を、安心と喜びに満ちたものへ切り替えていく「土台」になります。
焦らなくて大丈夫です。あなたのペースで、未来は変わります。
続けられない自分を責めない|習慣化のコツ
自己肯定感を育てるうえで大切なのは、「続ける工夫」です。
完璧じゃなくていい。やれるときに、やれる範囲で十分です。
- メモ帳に一言だけ書く
- いつもの行動とセットにする(歯磨き後など)
- 3日続いたら自分にご褒美を
- 「また明日から」で切り替える
- 続いた日をカレンダーで見える化する
習慣化は「完璧に続ける」ことではなく、
できる日を少しずつ増やしていくことです。
環境の力を侮らないで|あなたを否定する場所から離れていい
どんなに内面を整えても、環境があなたを否定し続けていたら、心はすり減ってしまいます。
たとえば、こんな環境があると回復は早くなります。
- 感謝を伝えてくれる人との関係
- 安心して話せる人がいる場
- 競争や評価の少ない空間
- 自分の価値観を尊重できる場所
- 人目を気にせず過ごせる静かな時間
「ここにいると落ち着く」
「この人と話すと安心する」
そう感じる空間や人を、少しずつ増やしていきましょう。
そして、もしあなたを否定する環境があるなら、
こっそり距離を置いていいんです。
👉 心理カウンセラーかぼのYouTubeチャンネルはこちらhttps://www.youtube.com/@cabo.psychology