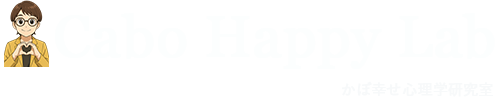「こんなに頑張っているのに、なぜかうまくいかない…」
「周りの人はスムーズにできているのに、自分だけ不器用で落ち込む…」
「理由は分からないけど、最近ずっと気分が沈みがち…」
もしあなたが、こんなふうに感じているなら――
あなたが悪いのではなく、“思考のクセ”が満足や幸せを遠ざけている可能性があります。
こんにちは。公認心理師の心理カウンセラー・かぼです。
この記事では、日常の中で多くの人が無意識にやってしまう「幸せを邪魔する思考パターン」を3つ紹介し、今日からできる改善方法をわかりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、
- 仕事がスムーズに進みやすくなった
- 決断が早くできるようになった
- ストレスが減った気がする
- 人間関係が少し楽になった
- 挑戦する回数が増えた
そんな変化のきっかけを持ち帰れるはずです。
思考のクセ①:完璧主義
完璧主義とは、
- 100%の結果を出さないと意味がない
- 少しでも不完全なら許せない
という思考のクセのことです。
完璧主義の人は、基本的に努力家です。真面目で、責任感も強い。
だからこそ、最初は成果が出やすい一方で、長期的には心と体をすり減らしやすくなります。
完璧主義がつらくなる理由
完璧主義を続けていると、いつも高すぎる目標を設定してしまい、常に全力になりやすいです。
その結果、
- 疲れやすい
- 燃え尽きやすい
- 達成できないと強く自分を責める
- 自己肯定感が下がる
さらに厄介なのは、目標を達成しても「まだ足りない」「もっとやらなきゃ」と感じて、満足ができなくなることです。
すると、いつしか心の中で、こんな声が大きくなっていきます。
「完璧にできないなら、やらない方がいい」
こうなると挑戦する回数が減り、チャンスや成果も減ってしまいます。
努力家な人ほど、このループに入りやすいので要注意です。
完璧主義の改善方法:「80%でOK」にする
完璧主義を手放す第一歩は、たった一つです。
「80%でOK」と考えること。
心理学では、こうした考えができる人をサティスファイサー(satisficer)と呼びます。
サティスファイサーとは、
「十分満足できる選択肢を見つけたら、それ以上は深追いしない」タイプのこと。
完璧を求めず「これで十分」と考える習慣が身につくと、心に余裕が生まれ、柔軟に動けるようになります。
完璧より「進化」を選んだスティーブ・ジョブズの例
ここで、Apple創業者スティーブ・ジョブズのエピソードを紹介します。
iPhoneが初めて発売されたのは2007年。
当時のiPhoneは画期的でしたが、今から見ると「足りない機能」がたくさんありました。
- コピーペースト機能がない
- 通信が遅い(当時最速の3Gに未対応)
- Apple Storeがなく、アプリ追加ができない
普通なら「全部そろってから出そう」と考えます。
でもジョブズは、未完成でもまず市場に出して、ユーザーの声を聞きながら改善していく道を選びました。
その結果、iPhoneは毎年進化し、機能は後から次々と追加され、世界的な大ヒットになりました。
完璧を目指すのではなく、進化し続けることを選んだわけです。
今日からできる合言葉
もしあなたが疲れてしまったとき、行き詰まったときは、こう思い出してみてください。
- 私はサティスファイサー
- 80%でOK
- 完璧より、進化
思考のクセ②:他人と比較するクセ
SNSを見て、こんなふうに感じたことはありませんか?
- 海外旅行、楽しそう…
- おしゃれでいいな…
- 恋人がいて幸せそう…
そして次の瞬間、
「それに比べて私は…」
そんなふうに落ち込んでしまう。
でも、これもあなたの性格が悪いわけではありません。
人は本能的に比べてしまう
人間は集団で生きる動物です。
他人と比べることで、自分の立ち位置や役割を確かめながら生き延びてきました。
つまり、比較してしまうのはある意味、自然な脳の働きです。
ただし、現代のSNSは「他人のキラキラした一瞬」だけが強調されます。
それを見て自分の現実と比べると、どうしても苦しくなります。
比較をやめるコツ:「昨日の自分」と比べる
他人と比べる代わりに、比べる相手を変えます。
「昨日の自分」と「今日の自分」を比べる
- 昨日より少し前進できたかな?
- 先週より成長した部分はある?
- 最近できた“小さな成功”は?
この視点を持つだけで、健全な自己評価ができるようになります。
おすすめ:成長日記(今日できたことを3つ書く)
とはいえ、頭で分かっても比較は止まりません。
そこでおすすめなのが、成長日記です。
毎日「今日できたこと」を3つ書きます。
たとえば、
- 昨日より5分早く起きられた
- 資料を1ページ多く作れた
- 今日は階段を使った
こうした小さな積み重ねを可視化すると、自己肯定感が回復し、他人との比較が自然と減っていきます。
思考のクセ③:過去や未来にとらわれる
過去の後悔、未来の不安は尽きないですよね。
- あのときああすればよかった
- 老後のお金が足りないかもしれない
- 仕事がなくなったらどうしよう
- この先うまくいくのかな
なぜ過去や未来を考えてしまうのか
脳は、生き残るために、過去の経験を振り返り、未来の危険を回避しようとします。
だからこそ、考えてしまうのは仕方のないことです。
ただ現代は悩みが複雑で長期化しやすく、脳が疲れ切ってしまいます。
ストレスホルモン「コルチゾール」が増える
過去や未来にとらわれ続けると、ストレスホルモンのコルチゾールが増えやすくなります。
コルチゾールが増えると、
- 免疫力の低下
- 睡眠障害
- 集中力・記憶力の低下
- イライラしやすくなる
- 社交性の低下
など、心身にさまざまな影響が出やすくなります。
解決の鍵は「今この瞬間」
幸せを感じられるのは、過去でも未来でもなく、
「今、この瞬間」だけです。
そこでおすすめなのが、マインドフルネスです。
マインドフルネスは難しくない
マインドフルネスというと座禅のようなイメージがありますが、もっとシンプルで大丈夫です。
- 深呼吸して呼吸に意識を向ける
- 食事の味や香りに集中する
- 散歩中に風の音や鳥の声に意識を向ける
こうして五感を使いながら「今ここ」に意識を戻すだけで、心は静かに整っていきます。
おすすめ:グランディング(5-4-3-2-1テクニック)
不安が強いときは、認知行動療法でよく使われるグランディングもおすすめです。
5-4-3-2-1テクニックは、五感を使って意識を「今」に戻す方法です。
- 見えるものを5つ探す(例:カーテン、時計、本、スマホ、机)
- 触れられるものを4つ触る(例:服の生地、床、コップ、髪の毛)
- 聞こえる音を3つ探す(例:時計の音、鳥の声、車の音)
- 香りを2つ意識する(例:ハンドクリーム、コーヒー)
- 味を1つ感じる(例:ガム、飲み物の後味)
ゆっくり行うことで、不安や後悔から距離を取れるようになります。
まとめ|幸せを邪魔する思考のクセ3つと改善法
最後に、今日の内容を振り返ります。
- ① 完璧主義 → 「80%でOK(サティスファイサー)」
- ② 他人と比較するクセ → 「昨日の自分と比べる/成長日記」
- ③ 過去や未来にとらわれる → 「マインドフルネス/グランディング」
これらはどれも、特別な才能はいりません。
日常の中で少しずつ試せるものばかりです。
あなたの毎日が、ほんの少しでも軽くなりますように。
YouTubeでも解説しています
今回の記事の内容は、YouTubeでも詳しく解説しています。
「読むだけだと続かない」「声で聞く方が落ち着く」という方は、ぜひ動画も見てみてください。
👉 心理カウンセラーかぼのYouTubeチャンネルはこちらhttps://www.youtube.com/@cabo.psychology