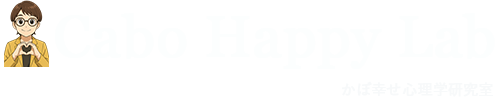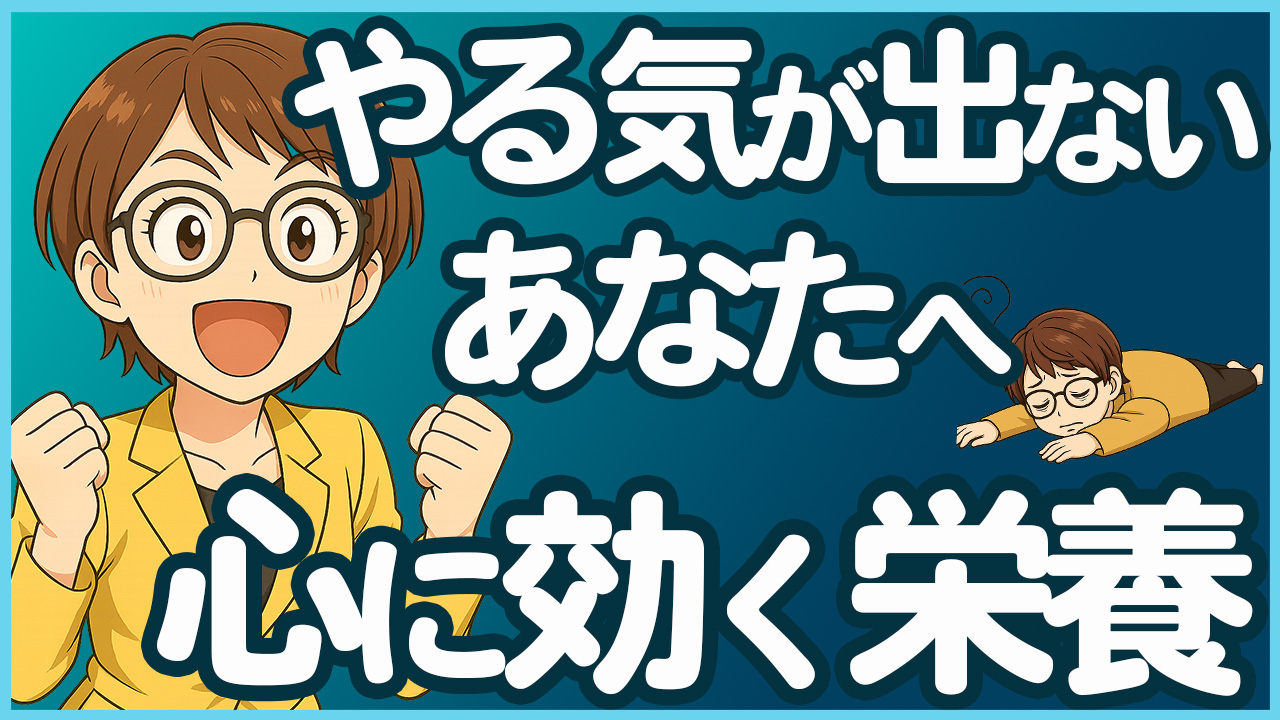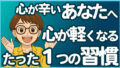こんにちは、公認心理師のかぼです。
「なんとなく気分が晴れない」「朝ベッドから起きるのがつらい」「頑張りたいのにやる気が出ない」そんなふうに感じたことはありませんか?
私自身、過去に病気の診断を受け、食生活を見直したことで心まで元気を取り戻した経験があります。その体験を通して強く実感したのは、「栄養は心にも効く」ということです。
脳は体重のわずか2%の大きさですが、全エネルギーの20%以上を使う器官。エネルギー源はもちろん食事からです。栄養が不足すれば心も不調に傾きやすくなります。今日は「心と食事の深い関係」を、研究と経験をもとに解説します。
1. オメガ3脂肪酸 ― 脳の潤滑油
サーモンやイワシ、アマニ油などに多く含まれるオメガ3脂肪酸は、心の健康に欠かせない栄養素です。神経細胞の膜を柔軟にし、情報伝達をスムーズにする働きがあります。これによって落ち着いた気分や前向きな思考を助けてくれます。
研究でも、オメガ3を摂取したうつ病患者の症状が改善したという報告があり、抗うつ薬と併用すると効果が高まることも示されています。日本の魚中心の食生活は、まさに理想的な形といえるでしょう。
2. ビタミンB群 ― 幸せホルモンをつくる力
ビタミンB群は豚肉、レバー、玄米、納豆などに豊富です。特にビタミンB6は「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンやドーパミンの材料となり、気分の安定に重要です。
ストレスが多いと消費されやすいため、不足すると気分の落ち込みやイライラにつながります。インスタント食品に偏る生活が続くと「なぜか元気が出ない」と感じるのはそのためかもしれません。忙しい人ほど意識的に取り入れたい栄養素です。
3. 鉄分 ― 意欲と集中力の土台
鉄分は酸素を運ぶ赤血球をつくるだけでなく、やる気や集中力を生む神経伝達物質の合成に不可欠です。特に女性は不足しやすく、貧血は心の不調にも直結します。
鉄分不足のサインには「疲れやすい」「気分が沈む」「集中力が続かない」などがあります。レバーや赤身肉、かつお、ほうれん草などを意識し、ビタミンCと一緒に摂ることで吸収率を高めましょう。
4. 発酵食品と腸内環境 ― 腸は第二の脳
「腸は第二の脳」といわれるほど、腸内環境はメンタルに影響します。腸にはセロトニンの9割以上が存在し、腸が整うことで気分も安定しやすくなるのです。
ヨーグルト、納豆、味噌、ぬか漬けなどの発酵食品は腸の善玉菌を増やします。毎朝の味噌汁や納豆ご飯といった小さな習慣が、実は大きな心の支えになるのです。
5. トリプトファンの真実 ― 単体よりバランスが大事
バナナやナッツに含まれるトリプトファンはセロトニンの材料ですが、単体で大量に摂っても脳内セロトニンは必ずしも増えません。大切なのは、栄養の組み合わせと生活習慣です。
バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠。これらが揃って初めて、栄養が力を発揮します。
まとめ:心と体に、今日できる小さな優しさを
オメガ3脂肪酸、ビタミンB群、鉄分、発酵食品。どれも心と体を整える大切な栄養素です。完璧でなくても大丈夫。
「朝食に納豆をプラスする」「魚料理を1品増やす」そんな小さな工夫から始めてみましょう。体に優しくすることは、心に優しくすることにつながります。
あなたの毎日が少しでも穏やかで明るくなりますように。
📺 YouTubeでも詳しく解説しています
この記事の内容をさらに詳しく知りたい方は、ぜひ私のYouTubeチャンネルをご覧ください。心が軽くなるヒントをたくさん発信しています。
👉 心理カウンセラーかぼのYouTubeチャンネルはこちらhttps://www.youtube.com/@cabo.psychology