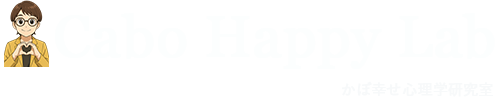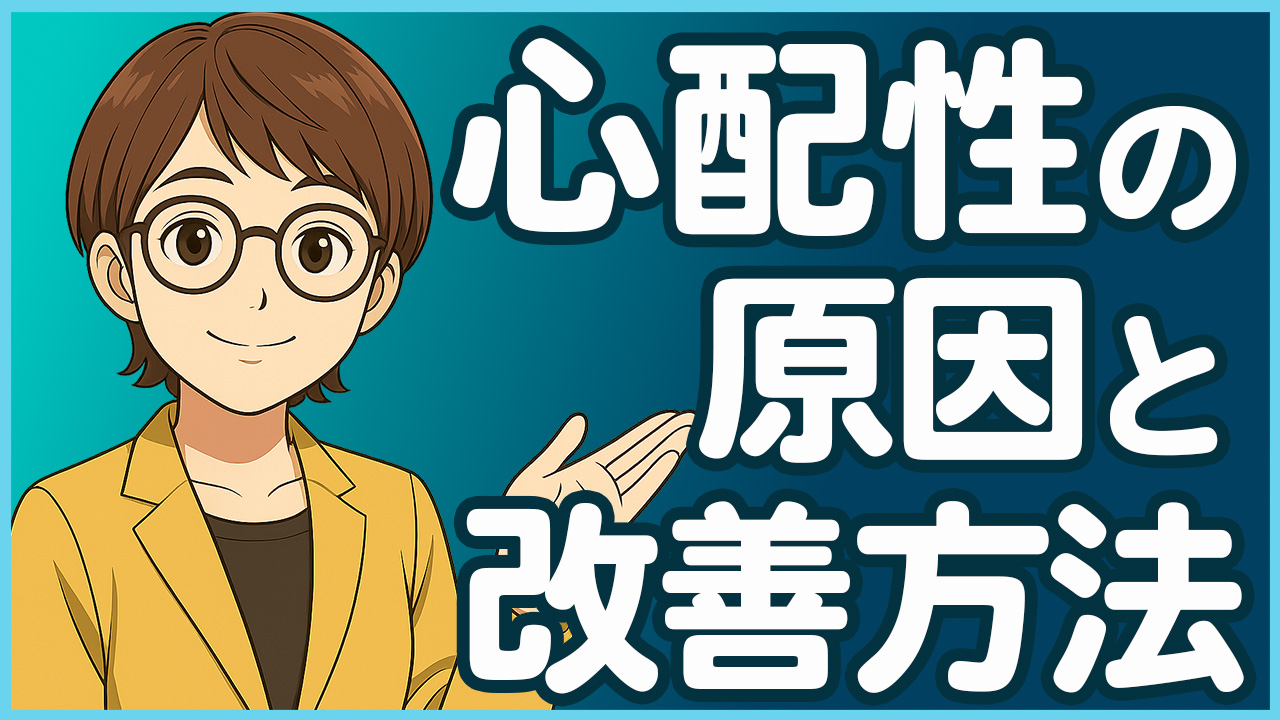こんにちは、公認心理師のかぼです。今日は「心配性の原因と改善法」というテーマでお話しします。
「心配で眠れない」
「考えても仕方がないと分かっているのに、頭から離れない」
──そんなふうに、不安な気持ちに振り回されてしまうこと、ありませんか?
心配性の状態が続くと、眠れなくなったり、疲れやすくなったり、集中力が下がったりと、
日常生活にじわじわ影響してきますよね。
「心配ばかりしてしまって、結局何も楽しめなかった」
そんな経験のある方も、多いのではないでしょうか。
まず最初にお伝えしたいのは、心配性は「性格だから仕方がない」とあきらめなくていい、ということです。
心配性には、ちゃんと理由があります。理由が分かれば、対処の方向性も見えてきます。
心のしくみを知ることで、誰でも少しずつラクになっていくことができるんです。
心配を手放せるようになると、何が変わるのか
心配が少しずつ手放せるようになると、生活の質は確実に変わっていきます。たとえば、次のようなメリットがあります。
- 夜、眠れるようになる(眠りが深くなる/寝つきが良くなる)
- 不安に引きずられず、自分のやりたいことに集中できる
- 自分を責める時間が減って、人間関係がラクになる
「たったそれだけ?」と思うかもしれません。けれど実は、この3つが戻ってくるだけで、心の回復力はぐっと上がります。
眠れるようになると脳が回復しやすくなり、集中力が戻り、余計な心配が減りやすくなる。
そして自分を責める時間が減ると、人との距離感も自然に整いやすくなります。
心配性は、悪循環で強くなりやすい一方で、良い循環に乗ると、驚くほど軽くなっていくこともあるんです。
私自身も、かつては強い心配性でした
私自身、かつては相当な心配性でした。特に強く覚えているのが学生時代のことです。
私は中学・高校と不登校を経験し、一時期は児童相談所にも預けられていました。
そのころは、毎日が不安でいっぱいで──
「このまま私なんて、生きていけるんだろうか」
──そんなふうに、悩んでは落ち込む毎日が、長く続いたんです。
頭では「なんとかしなきゃ」と思うのに、体が動かない。
人と会うのも怖い。未来のことを考えると、胸が苦しくなる。
心配って、ただの思考じゃないんですよね。身体感覚としても、しんどさが残ります。
心配性の方が抱える苦しさは、決して甘えではありません。
でも、心理学を学ぶ中で私はようやく、「心配にはちゃんと理由がある」ということに気づきました。
そして今では、「あの頃の私に教えてあげたかった」と思うような、いくつかの大切な気づきがあります。
この記事では、そんな私自身の経験も交えながら、
「心配性の本当の正体」と「どうやって心を軽くしていくか」について、やさしくお話ししていきます。
それでは始めましょう。
心配性の本当の原因|無意識に入ってくる情報の力
心配性の根っこにある原因のひとつに、「スプラリミナル知覚」という現象があります。
あまり聞きなれない言葉かもしれませんね。
これは簡単に言うと、「私たちが気づかないうちに、情報が心に届いている」という現象のことを指します。
たとえば、テレビのニュース、SNSの投稿、通勤電車の広告、友人との何気ない会話──。
これらの情報が、私たちの“目”や“耳”を通して、無意識のうちに心に入ってきます。
そして恐ろしいことに、ネガティブな情報ほど強く心に残るんです。
これは、人間の脳が「危険を見落とさない」ようにできているからです。
大昔の環境では、危険を見落とすことは生死に関わりました。だから脳は、ネガティブ情報を優先的に記憶します。
意識的には「もう忘れた」と思っていることでも、無意識の中ではずっと蓄積されていて、
それが“心の背景音”のように、不安や心配としてにじみ出してくるんですね。
たとえば、ある日突然「将来が不安だ」と感じたとしても、その原因は「今この瞬間の出来事」ではなく、
昨日見た暗いニュース、1週間前に聞いた噂話、1ヶ月前に見た投稿──
そういった情報の積み重ねかもしれないのです。
つまり、心配性は「考え方のクセ」だけではなく、
心に入ってくる情報の環境によって作られている面が大きいのです。
ここに気づけると、「自分が弱いからだ」と責める必要がなくなります。
なぜ日本人に心配性が多いのか|文化と生活環境の影響
日本人は心配性になりやすい人が多いんです。
日本人が心配性になりやすい理由には、「文化的背景」や「遺伝的傾向」もあると言われています。
ある研究によれば、日本人のおよそ8割が「不安を感じやすい遺伝子型」を持っているそうです。
ただ、ここで大事なのは、だからといって「もうどうしようもない」というわけではない、ということです。
実はそれ以上に影響が大きいのが、私たちの「生活環境」と「情報の入り方」なんです。
日本では、「心配することは真面目な証拠」とされやすい文化があります。
「先のことを考えて備えなさい」「油断してはいけない」──そんな言葉を、小さなころから聞かされて育ってきた人も多いはずです。
さらに、テレビをつければ事件・事故・病気の話題が次々と流れ、SNSでは誹謗中傷や炎上の話題があふれています。
こうした情報に日々さらされていると、無意識は「また何か悪いことが起きるかもしれない」「今のままでは危ない」と、
“危険信号”を鳴らし続けてしまうのです。
まさに、心の中のコップに、じわじわと黒いインクが溜まっていくようなイメージですね。
そして、そのコップがいっぱいになると、小さな出来事がきっかけになって、心配があふれ出てしまいます。
心配性のメカニズム|「心のコップ」があふれるとき
心をコップに例えてご説明いたしますね。
心には2つの層があります。
表層は、意識──つまり、自分で気づいている思考や感情。
そして、深層には無意識(潜在意識)があって、そこは情報の倉庫のようなもの。
毎日少しずつネガティブな情報がこの無意識の層に溜まっていくと、やがてコップがいっぱいになり、
ある日、ほんの些細な出来事──たとえば、
「朝のゴミ出しで近所の人に挨拶されなかった」
「仕事で小さなミスをした」
そんなことをきっかけに、不安がドバっとあふれ出す。
これは、その出来事自体が悪いのではなく、「心のコップ」があふれただけなんです。
コップが余裕のある状態なら、同じ出来事が起きても、ここまで大きく反応しないことも多いでしょう。
私自身、昔はこの“あふれた状態”にすぐパニックになっていました。
「どうしよう」「もうダメだ」「終わった」そんなふうに、頭の中の最悪シナリオが暴走してしまう。
でも今では、「ああ、心が疲れてるサインだな」と気づくことができるようになりました。
この“気づき”がとても大切です。
心配が出たときに「私がダメだから」ではなく、
「今、心のコップが満杯なんだ」と理解できるだけで、安心感が少し戻ってきます。
心配性を改善する方法|コップに溜まるネガティブ情報を減らす
では、どうすればその「コップにたまったネガティブ情報」を減らしていけるのでしょうか?
ここからは、私が実際にやってみて効果を感じた方法を3つ、ご紹介します。
どれも、特別なスキルやお金は必要ありません。
“ちょっとした習慣の見直し”だけで、心はずいぶん軽くなるものなんです。
【1】テレビの見方を変える|ニュースを「義務」にしない
まずは、毎日何気なくつけているテレビから。
特にニュース番組やワイドショーは、私たちの心に大きな影響を与えています。
「○○の事件がまた発生」
「△△で感染拡大」
「物価高騰で生活が苦しい」
──どのチャンネルを回しても暗い話題が続くと、無意識のうちに「世界は不安だらけ」と思ってしまいます。
私はあるときから、ニュースを見るのをやめました。
と言っても、全部を遮断するわけではなく、「今はこれ以上見たくない」と感じた時点で、チャンネルを変えるようにしたんです。
代わりに見るのは、自然番組や旅番組、動物のドキュメンタリー。
あるいは、ふんわり笑えるお笑い番組や料理番組。
そういう映像にふれていると、ふしぎと呼吸が深くなり、心の緊張が少しずつゆるんでいくのを感じました。
「見なければいけない」と義務のように思っていたニュース番組も、実は「今の自分には必要ない」と気づくことができたんですね。
情報収集は大切です。でも、心が壊れてまで集める必要はありません。
ニュースを“必要な量だけ”にすることが、心配性の改善にはとても効果的です。
【2】SNSやネットの情報を取捨選択する|“心がほっとする”を基準に
次に見直したのは、スマートフォンの使い方でした。
SNSを何となく開いて、スクロールしていたら、誰かの怒りの投稿や、攻撃的なコメントに出会ってしまう。
「〇〇最低」「誰それが炎上」そんなワードに触れた瞬間、胸の奥がざわついて、不安がじわじわと広がっていく──。
心配性の人ほど、こうした情報に敏感に反応してしまいやすいんです。
だから私は、SNSのフォローリストを整理しました。
「この人の投稿を見たあと、心があたたかくなるか」
「それとも疲れてしまうか」
──そんな視点で、思い切って整理したんです。
たとえば、自然の写真を投稿している人や、かわいい動物の動画をあげているアカウント。
日々の小さな幸せを綴っている人、前向きな言葉を発信している人。
そういう“心がほっとする投稿”だけを見ていると、不思議と一日が優しく感じられるようになります。
ネットは便利な反面、「心の毒」になってしまうこともあるので、意識して“選ぶ”姿勢がとても大切です。
そしてもう一つおすすめしたいのは、「目的なく開く時間」を減らすことです。
心配が強いときほど、人は無意識にスマホを開きがちです。
その瞬間にネガティブ情報を浴びると、コップはさらに満杯になってしまいます。
「見るものを変える」「見る時間を変える」
この2つだけでも、心の状態は確実に変わっていきます。
【3】人間関係を整える|“会話”は最強の情報源
そして最後は、「人との距離感」です。
これは多くの方が気づきにくいところなのですが、実は一番心に影響を与えるのが、身近な人との会話だったりします。
たとえば、日常的に「人の悪口」や「陰口」「誰かを見下すような言葉」が多い人と一緒にいると、
自分は言われていなくても、心の中にじわっと“黒い色”が染み込んできます。
私も昔、職場でそういう雰囲気に耐えられず、帰宅後にどっと疲れてしまうことがありました。
最初は、「私が気にしすぎなのかな」と思っていたのですが、心が疲れる感覚は正直でした。
それからは、「少し距離を置く」「会話の内容を変える」「関係を見直す」ことを、自分に許すようにしたんです。
もちろん、すべての人間関係をすぐに断ち切ることは難しいかもしれません。
でも、自分を傷つける関係から少しずつ離れることは、“自分を大切にする第一歩”だと今では感じています。
“誰と一緒にいるか”は、“どんな情報を心に入れるか”と同じくらい重要なんです。
会話は、ニュースよりもSNSよりも、心に深く入り込みます。
だからこそ、あなたの心がすり減る場所からは、少しずつ距離を取っていいんです。
心配性は「性格」ではなく「積み重ね」でできている
このように、「テレビ・ネット・人間関係」。
この3つの“心に入ってくる情報の入口”を少し意識して整えるだけで、心のコップにたまるネガティブな水は、ぐっと減らすことができます。
「心が弱いから心配性なんだ」──そう思っていたあの頃の私に、そっと伝えたい。
「心の環境を変えるだけで、きっとラクになれるよ」って。
まとめ|今日からできる小さな一歩
心配性とは、「生まれつきの性格」ではなく、「心に入ってきた情報の積み重ね」なのです。
つまり、私たちには“心を整える力”が、もともとちゃんと備わっているんです。
だからこそ、心配性な自分を責めないでくださいね。
不安が強いときは、あなたの心が弱いのではなく、心のコップがいっぱいになっているだけかもしれません。
「朝食のお味噌汁がおいしかった」
「部屋の観葉植物が大きくなったなぁ」
「コンビニの店員さんの笑顔、ちょっと嬉しかったな」
「今夜は好きなアロマを入れて、ゆっくりお風呂に入ろう」
──そんなふうに、自分の中に“あたたかいもの”をひとつずつ取り入れてあげてください。
どんなに小さくても構いません。
ポジティブな情報を「意識して集める」ことが、心のコップを少しずつ透明にしていく第一歩になります。
そして、「心に入れる情報」を、毎日の食事のように自己管理していきましょう。
不安なときこそ、やさしい言葉、落ち着いた音楽、心がほっとする映像──
そういうもので、自分の心を満たしてあげてください。
あなたの心がほっと安心できることを祈っています。
今日、あなたが心の中に入れたポジティブを1つ、コメントで書いていただけたら嬉しいです。
今日のお話が、少しでもお役に立てましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
YouTubeでも詳しく解説しています
この記事の内容は、YouTubeでもやさしく解説しています。
読むより「声で聞くほうが安心する」という方も多いと思います。
ぜひYouTube動画もあわせてご覧ください。
👉 心理カウンセラーかぼのYouTubeチャンネルはこちらhttps://www.youtube.com/@cabo.psychology