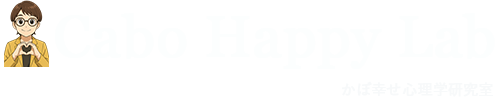「このままで大丈夫?」「将来が心配…」「私の育て方が悪かったのかな」
子どもが不登校になると、親は不安と焦りで頭がいっぱいになります。
でも実は、その焦りから取ってしまう行動が、子どもの心をさらに追い詰めてしまうことがあります。
この記事では、不登校の親が絶対にやってはいけない3つのことを、心理学の視点でわかりやすく解説します。
不登校が増えている今、親が「間違えやすい」理由
近年、日本では子どもの数は減っているのに、不登校の子どもは増え続けています。
もし自分の子どもが学校へ行けなくなったら、親として心配になるのは当然です。
- どうすればいいのかわからない
- このまま将来はどうなるのか不安
- 何が原因だったのか答えがほしい
こうした気持ちは、ごく自然な反応です。
ただ、親が「何とかしなきゃ」と頑張りすぎるほど、対応を間違えてしまうことがあります。
私自身も中学・高校時代に不登校を経験しました。
当時は「登校拒否」や「非行」などの言葉で語られる時代で、本人も家族も苦しい時間だったのを覚えています。
その経験もふまえて、今このページにたどり着いたあなたへ、心から伝えたいことがあります。
それは親が「正しい方向」で関われば、子どもは回復していけるということです。
不登校の親が絶対にやってはいけないこと① 他の子と比べる
まず1つ目は、「他の子と比べる」です。
たとえば、こんな言葉をつい言ってしまうことがあります。
「あきらちゃんは元気に学校行ってるのに、なんであなたは行けないの?」
これは子どもの心を強く傷つけるNGワードです。
なぜなら、子どもはすでに「学校に行けない自分はダメなんだ」と思い込んでいることが多いからです。
大人だって、比べられるのはつらいですよね。
私も子どもの頃、「お姉ちゃんはちゃんとピアノの練習して弾けるのに、なんであなたはできないの?」と言われて、胸が苦しくなったのを覚えています。
今なら「バスケは私の方が得意だったのにな」と思えますが、当時は違いました。
「私は何をやってもダメなんだ」と感じてしまったんです。
比べるなら「昨日の本人」と比べてください
不登校の子どもにとって大切なのは、小さな前進を認めてもらえることです。
比べる相手は「他の子」ではなく、「昨日のその子自身」にしてあげてください。
- 昨日より少し笑顔が増えた
- 部屋から出てご飯を食べられた
- 好きなことに少し興味を持てた
こうした小さな変化を認めることが、子どもの自信につながります。
「学校に行けてないからダメ」ではなく、
「学校には行けていないけれど、家で少しずつ成長できている」
そう思える感覚が育っていくと、回復の土台ができていきます。
不登校の親が絶対にやってはいけないこと② 甘やかしすぎる or 厳しすぎる
2つ目は、「極端な対応」です。
不登校の子どもへの関わり方は、本当に難しいですよね。
親の気持ちが揺れるほど、対応は両極端になりやすいです。
厳しすぎると、子どもは「自己否定」へ
「いつまで休んでるの?そんなんじゃ将来ダメになるよ!」
こう言われると子どもは追い詰められ、自己否定感が強まりやすくなります。
その結果、ますます動けなくなってしまうこともあります。
甘やかしすぎると、社会との距離が広がる
「学校に行かなくてもいいよ。ずっと家にいても大丈夫だよ」
優しさから言っている言葉でも、状況によっては社会との距離が遠くなる方向へ進んでしまうことがあります。
そのまま孤立しやすくなるケースもあります。
おすすめは「支援的な親(サポーティブ・ペアレンティング)」
大切なのは、子どもの気持ちに寄り添いながら、無理のない範囲で生活と社会をつなぎ直すことです。
心理学では、バランスの取れた育児スタイルとして「支援的な親(サポーティブ・ペアレンティング)」が推奨されています。
これは、子どもの自主性を尊重しつつ、必要なサポートを適切に提供する関わり方です。
支援的な親の5つのポイント
- 温かい関係を築く(心理的安全性)
まずは「安心して話せる環境」を作ることが最優先です。
親は答えを出す役ではなく、聞く立場にまわる。ここがとても大切です。 - 適度なルールを設ける(構造化)
生活の土台が崩れると回復が難しくなります。
たとえば「午前中には起きる」「ゲームは1日1時間」など、できる範囲で整えていきましょう。
可能なら子ども自身が決められる形がベストです。 - 子どもの自信を育てる(自己効力感)
「やればできる」という感覚は、小さな成功体験から育ちます。
「ご飯をしっかり食べられたね」「時間を守れたね」など、前進を言葉にして伝えましょう。 - 自主性を尊重する(自律支援)
子どもが「自分で選べる」と感じると、回復の力が戻ってきます。
「学校に行くか行かないか」ではなく、
「今日はオンラインにする?」「フリースクールもあるよ」「家では何をして過ごしたい?」など、選択肢を小さく提示するのがコツです。 - 長期的な視点で見守る(成長の過程を重視)
不登校は短距離走ではなく、回復のプロセスです。
その子のペースで進むことを尊重しながら、タイミングを見て支える姿勢が大切です。
すべて完璧にやろうとしなくて大丈夫です。
できそうなところから少しずつ試してみてください。
不登校の親が絶対にやってはいけないこと③ すぐに解決しようとする
3つ目は、「すぐに解決しようとする」です。
親としては「どうすれば学校に行けるようになる?」と考えるのが自然です。
でも、ここが大きな落とし穴になりやすいのです。
不登校の背景には、たとえば次のような要因が複雑に絡みます。
- 友人関係
- 家庭内のストレス
- 体調の問題
- 勉強のプレッシャー
- 発達特性
- 心のエネルギー不足
それなのに「とにかく学校へ戻さなきゃ」と動くと、子どもはプレッシャーでさらに苦しくなることがあります。
まずやるべきは「理解すること」
解決よりも先に大切なのは、子どもの状態を理解することです。
- どんな気持ちでいるのか
- 何がつらいのか
- 何をしていると安心するのか
じっくり耳を傾けることで、子どもは「わかってもらえた」と感じられます。
また、話すこと自体が感情の整理につながり、少しずつ気持ちが落ち着いていきます。
小さな一歩を一緒に探す
子どもが話し終えたら、「今できそうなこと」を一緒に探していきましょう。
- 学校の時間に玄関を3メートルだけ出てみる
- フリースクールやオンライン学習を一緒に探す
- 図書館・カフェ・自然など外に出る機会を作る
- 趣味や習い事など、好きなことの芽を見つける
- スクールカウンセラーや専門家に相談する
ポイントは、親が決めるのではなく、子どもが「自分で決めた」と感じられる形にすることです。
理由をうまく説明できない子も多い
不登校の子どもは、自分でも理由がわからないことがあります。
- なんとなく行きたくないけど説明できない
- 友達関係に違和感があってもうまく言葉にできない
- 疲れているけど整理できない
これは決して珍しいことではありません。
大人でも限界まで疲れていることに気づけないことがありますよね。
だからこそ、無理に理由を聞き出さず、子どもが自分の気持ちを整理できるように支えることが大切です。
最後に:親が自分を責めないでください
不登校の相談に来られる親御さんの多くが、こう言います。
「私の育て方が悪かったから、子どもが不登校になってしまったんです…」
でも、どうか自分を責めないでください。
不登校は、親子関係だけで起こるものではありません。
学校環境、社会構造、教育の仕組み、さまざまな要素が絡んでいます。
不登校は「家庭だけの問題」ではなく、社会全体で向き合うべき課題です。
今つらい気持ちを抱えているあなたも、ひとりで背負わないでくださいね。
まとめ|不登校の親が絶対にやってはいけない3つのこと
最後に、今日の内容をまとめます。
- 他の子と比べる
- 甘やかしすぎる or 厳しすぎる
- すぐに解決しようとする
大切なのは、子どもの気持ちを尊重しながら、焦らず、安心できる環境を整えること。
それが回復への第一歩になります。
YouTubeでも解説しています(動画で見たい方へ)
今回の記事の内容は、YouTubeでもわかりやすくお話ししています。
文字よりも動画のほうがスッと入る方もいると思いますので、よかったらこちらもご覧ください。
👉 心理カウンセラーかぼのYouTubeチャンネルはこちらhttps://www.youtube.com/@cabo.psychology