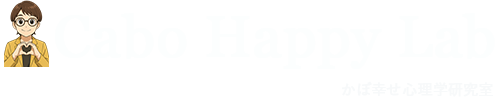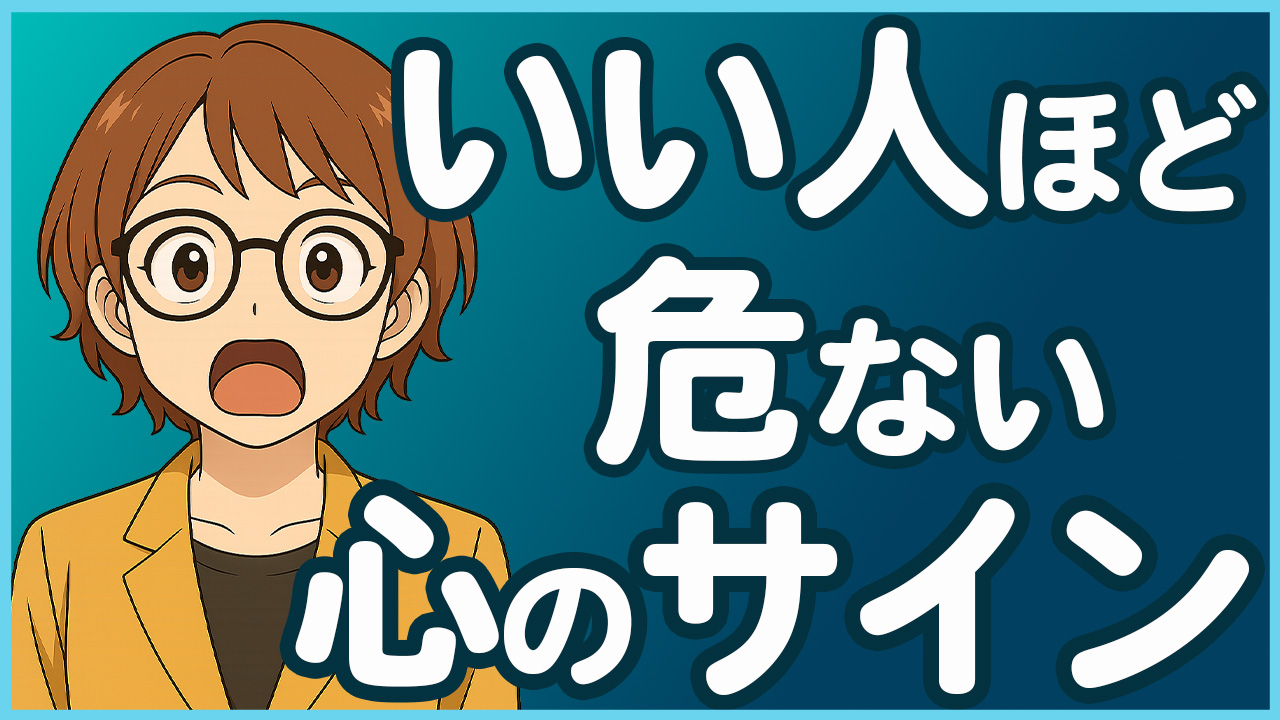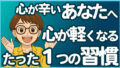夜、布団に入って目を閉じた瞬間。
ふと心がざわついて、今日の出来事が頭の中で何度もリピートされる――。
「また今日も、あれができなかった」
「あのとき、ちゃんと断れなかった」
そんなふうに、自分を責める声が止まらなくなる日ってありませんか?
誰にも迷惑をかけたくない。嫌われたくない。
だから今日も笑顔で頑張った。
だけど家に帰ると、どっと疲れて動けなくなる。
実は今、そんな「頑張りすぎる人」が心を壊してしまうケースが増えています。
そして特に、真面目で責任感が強く、人の期待に応えようとする“いい人”ほど、心が静かにすり減っていくのです。
こんにちは。公認心理師のかぼです。
私は元教員で、これまでに3回のがん治療を経験してきました。
身体だけでなく、心の限界とも何度も向き合ってきた中で痛感したことがあります。
それは――心の限界は、自分でも気づきにくいということです。
「私はまだ大丈夫」と思っていた裏側で、心と身体は静かに崩れていくことがあります。
この記事では、なぜ頑張りすぎる人ほど心を壊しやすいのかを心理学と脳科学の視点から解説し、
心が折れてしまう前にできる具体的な対処法を3つ紹介します。
頑張りすぎる人に多い「こころのクセ」とは?
頑張りすぎる人には、実は共通する特徴があります。
あなたにも思い当たるものがあるかもしれません。
- 「ちゃんとしなきゃ」「迷惑をかけちゃいけない」が口癖
- 小さなミスでも必要以上に自分を責める
- 頼るのが苦手で、何でも自分で抱え込む
- 弱音を吐けず「大丈夫そうな自分」を演じてしまう
こうした状態は心理学では「過剰適応」と呼ばれます。
また、人に合わせすぎて自分を後回しにしてしまう背景には、回避型の愛着スタイルが関係していることもあります。
「自分を犠牲にしてでも人に合わせる」
そのクセが、知らないうちにあなた自身を追い詰めてしまうのです。
「頑張らなきゃスイッチ」はどこで生まれるの?
この頑張りすぎる傾向は、性格の問題ではなく、
子どもの頃の経験や環境に根づいていることがよくあります。
- 「いい子にしていなさい」と言われ続けてきた
- 親の期待を裏切らないように、自分の気持ちを抑えてきた
- 家庭が不安定で「自分がしっかりしなければ」と思っていた
こうした経験が積み重なると、心の奥にこんな信念が刻まれていきます。
「私は価値ある存在でいなければいけない」
「弱い自分はダメなんだ」
そして大人になってからも、
その思い込みは「努力」「責任感」「優しさ」という形で表面化します。
頑張り続けると脳と心に起きる「見えない変化」
「疲れてるけど、まだ頑張れる」
そう思って走り続けると、脳と身体には確実に影響が出ます。
私たちの脳には、恐怖や不安を感じ取るセンサーのような働きをする扁桃体(へんとうたい)があります。
この扁桃体は本来、危険を察知して命を守るための大切な仕組みです。
しかし、慢性的なストレスが続くと扁桃体が過敏になり、
ほんの小さな刺激にも「危険だ!」と反応するようになります。
さらに、冷静な判断を担う前頭前野の働きが落ちることで、
不安や焦りに飲み込まれやすくなっていきます。
そしてストレスホルモンであるコルチゾールが出続けると、
記憶を司る海馬にも悪影響が出ることがあります。
この状態が続くと、次のような症状が起こりやすくなります。
- 眠れない(睡眠障害)
- イライラや不安が強くなる
- 頭がぼーっとする
- 物事に興味が持てない
- 何をしても楽しく感じられない
そして怖いのは、この状態の人ほどこう思いがちだということです。
「まだ頑張れる」
「迷惑をかけられない」
「私がやらなきゃ」
本当は、心が限界に近づいているサインなのに、
真面目な人ほどそれを努力で上書きしてしまうのです。
心が壊れる前にできること【今すぐできる3つ】
ここからは、心が折れてしまう前にできる対処法を3つ紹介します。
特別な才能はいりません。今日からできるものばかりです。
① 1日5分「自分の状態に気づく時間」を持つ
まずは、ほんの5分でいいので呼吸を整えながら、
自分にこう問いかけてみてください。
「今、私はどんな気持ち?」
「体はどんな感じ?」
「無理してるところはない?」
これはマインドフルネスの基本で、
自分の心の状態を“見える化”する習慣です。
マインドフルネスは、扁桃体の過活動を落ち着かせ、
前頭前野の働きを取り戻す助けにもなります。
② 自分をねぎらう言葉をかける(セルフ・コンパッション)
頑張りすぎる人ほど、自分に厳しい言葉をかけてしまいます。
だからこそ意識して、逆の言葉をかけてあげてください。
「今日も一日、よく頑張ったね」
「疲れてるのにやり切ったね」
「それでも生きてるだけで偉いよ」
自分への思いやり(セルフ・コンパッション)は、
心の回復力を高め、うつ症状の軽減にも役立つとされています。
私は毎晩、手帳に「今日できたこと」「嬉しかったこと」「ありがとうと思えたこと」を3つ書いています。
これはスリーグッドシングスと呼ばれる心理学的な方法で、幸福感を育てる習慣としてもおすすめです。
③ 弱音を吐ける相手を「一人だけ」持つ
大切なのは「何人いるか」ではありません。
本音を言っても大丈夫な相手が一人いるかです。
人に話すことは、感情を「放す」ことにもつながります。
抱え込んでいるものを言葉にするだけで、心が少し軽くなることがあります。
もし話せる相手がいない場合は、
紙に書くことでも十分効果があります。
「こんなこと思っちゃダメ」ではなく、
「今、私はそう感じてるんだね」と受け止める練習をしてみてください。
まとめ:あなたが壊れそうなのは弱いからじゃない
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
最後に一番大切なことをお伝えします。
心が壊れてしまうのは、弱いからではありません。
むしろ、頑張り屋さんで、誰かのために一生懸命な、優しい人ほど壊れやすいのです。
だからこそ、自分にこう言ってあげてください。
「休んでもいい」
「頼ってもいい」
「泣いてもいい」
その小さな許可が、あなたの心を守ってくれます。
あなたの明日が、少しでも穏やかでありますように。
YouTubeでも解説しています(動画はこちら)
今回の記事の内容は、YouTubeでもやさしく解説しています。
音声で聞きたい方、落ち着いた雰囲気で学びたい方は、ぜひ動画もご覧ください。
👉 心理カウンセラーかぼのYouTubeチャンネルはこちらhttps://www.youtube.com/@cabo.psychology